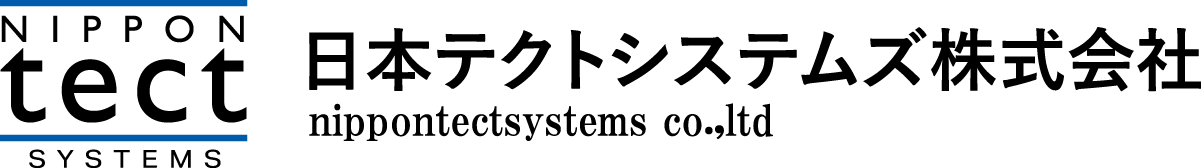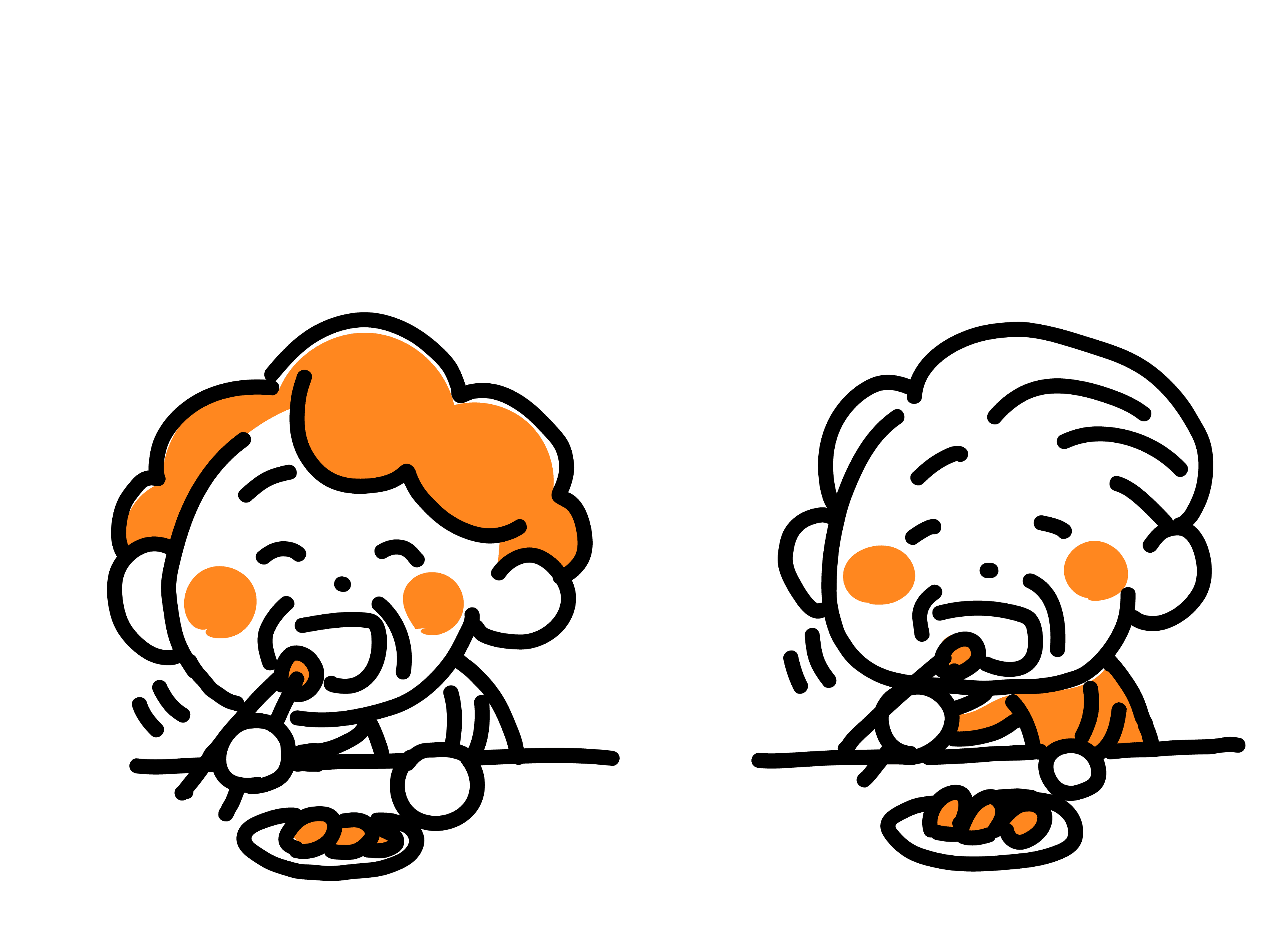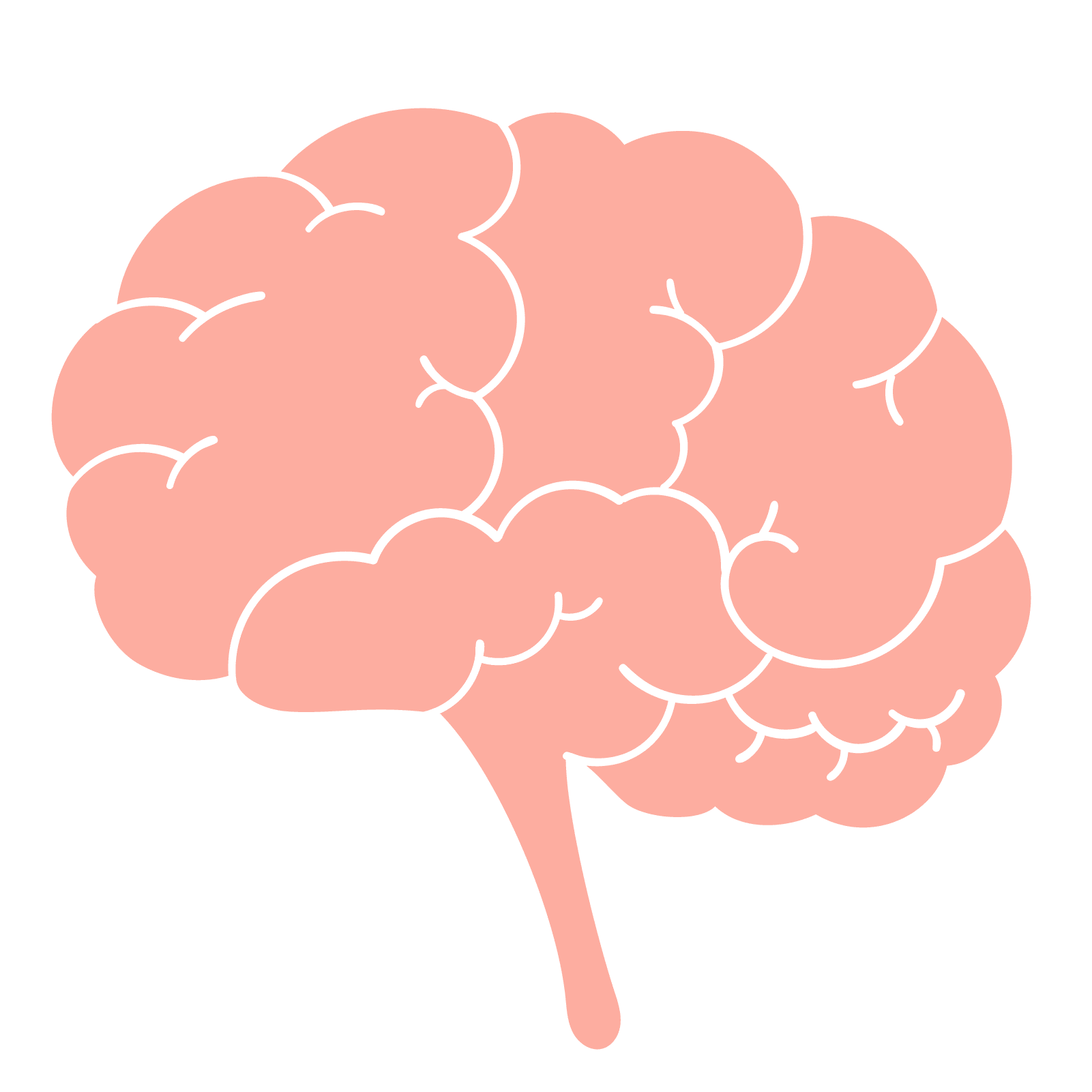適切な水分補給と便利グッズ
2025.09.16

本日は、今の時期に、特に意識していただく必要のある「水分補給」についてお話します。皆様水分を取っていますか?「はい」と自信たっぷりにお答えいただくことも多いのですが、少ない方が多いのが実情です・・・。
喉が渇いている状態はすでに脱水と同じ状態ですので、喉が渇く前にこまめに水分摂取をすることが推奨されます。
味のない飲み物は嫌だ、こまめに水分補給をすることが難しい…というご意見をお伺いすることがありますので、今日は効果的な水分摂取の方法と、水分摂取に便利なグッズをご紹介します。
効果的な水分摂取の方法とは?
水分摂取はご自身の評価に比べて実は意外と少ないことが多いのは、先にお伝えした通りです。それほど水分は意識をしないと摂れないものなのです。
効果的な水分摂取とは、ただ「たくさん飲むこと」ではなく、「必要な量を、適切なタイミングで、バランスよく摂ること」です。次のポイントを押さえて、体に無理なく水分を補いましょう。
〇基本のポイント〇
- 1日の目安量:一般的に1.2~2リットル程度(体格・気温・活動量によって前後します)
- こまめに摂取:一度に大量に飲むのではなく、1日を通して少しずつ分けて飲むのが理想的。
- 寝起き・入浴後・運動後・就寝前など、水分が失われやすいタイミングは特に意識的に補給。
注意点としては…
- 暑い時期や運動後には、水分だけではなく、塩分やミネラルも同時に失われやすくなります。必要に応じて塩分タブレットや梅干しなども同時に摂取していただくことが推奨されます。
- 色の濃いお茶やアルコール、コーヒーなどは利尿作用があります。これらは水分としてのカウントするのではなく、嗜好品としてのカウントになりますので、お気を付けください。
〇飲み物の選び方〇
| シーン | おすすめの飲み物 |
| 朝起きた時 | 白湯や常温の水 |
| 外出中 | 水、麦茶、スポーツドリンク(軽めの濃度) |
| 食事中 | 食べ物に含まれる水分+お茶など |
| 運動後 | 水+少量の塩分や糖分 |
食事からも水分は摂取できますので、飲水は苦手という方は、毎食必ず味噌汁やスープ、フルーツなどを摂るようにするのもおすすめです。
★水分摂取に便利なグッズ
先ほどもお伝えした通り、水分を意識して取る事は至難の業です。飲水のたびにリビングやキッチンに取りにいかなければならないとなると、何とめんどくさいことか・・・(私だけでしょうか?)。そこで簡単に水分摂取ができる便利なグッズをご紹介します。
すでに使っている、持っている方も多いかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。
*タイムマーカー付きボトル
もちろん水筒やペットボトルでも良いのですが…飲水量や、摂取時間が記載されているボトルが市販されています。時間に追われている感は否めませんが(笑)「意識化」という意味ではとても役立ちます。
水分摂取が難しい方は一度検討いただいてもよいかもしれません。毎日使うものですので、1日に1回は必ず洗浄してくださいね。
*水ゼリー(味付き、味なしともに)
脳卒中後や加齢に伴う嚥下機能の低下により、水分がうまく摂取できない方に関しては、すでにとろみがついたゼリー状のものもおすすめです。
1回分がわかりやすいので、飲みやすさだけではなく1回の飲水量をカウントするのにも有効です。また、ご自身の使用するとろみの粘度と変わらないようであれば、毎回作る手間も省けますね。
最後に、頻尿が原因で飲水を制限してしまう要因になっている例もしばしばお目にかかります。基本的に摂った水分は排出されるのが常です。
「一気に」ではなく「こまめに」摂取していただくことで水分の吸収率が高まりますので、それほど頻尿になる事はないかと思います。
また夜間の熱中症対策には、寝る前の1杯の水が大切とされますが、寝る直前ではなく、2時間前に済ませていただくと睡眠もしっかり確保されると思います。
長くなりましたが、本日もお読みいただきありがとうございました。
■執筆者情報
この記事は、医療法人バディ公式LINE「ケアコミ」の内容を引用しております。

医療法人バディ 認知症部門副部長
廣島真柄(言語聴覚士・認知症ケア専門士)
都内の総合病院に言語聴覚士として15年以上勤務。主に急性期病院で脳卒中、神経難病の患者のリハビリを担当しながら、認知症疾患医療センターでもの忘れ外来の検査や入院患者の認知症ケアを担当。2021年に医療法人バディに入職。コミュニケーションを主軸とした認知症の非薬物療法に取り組む。

医療法人バディ https://buddymedical.jp/
2019年設立。横浜市、鎌倉市に3つの脳外科クリニックと認知症部門を展開。2023年より、居宅介護支援事業、訪問リハビリ。2024年より訪問看護部門を開設。