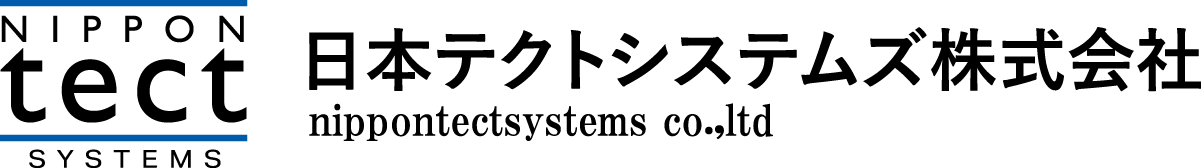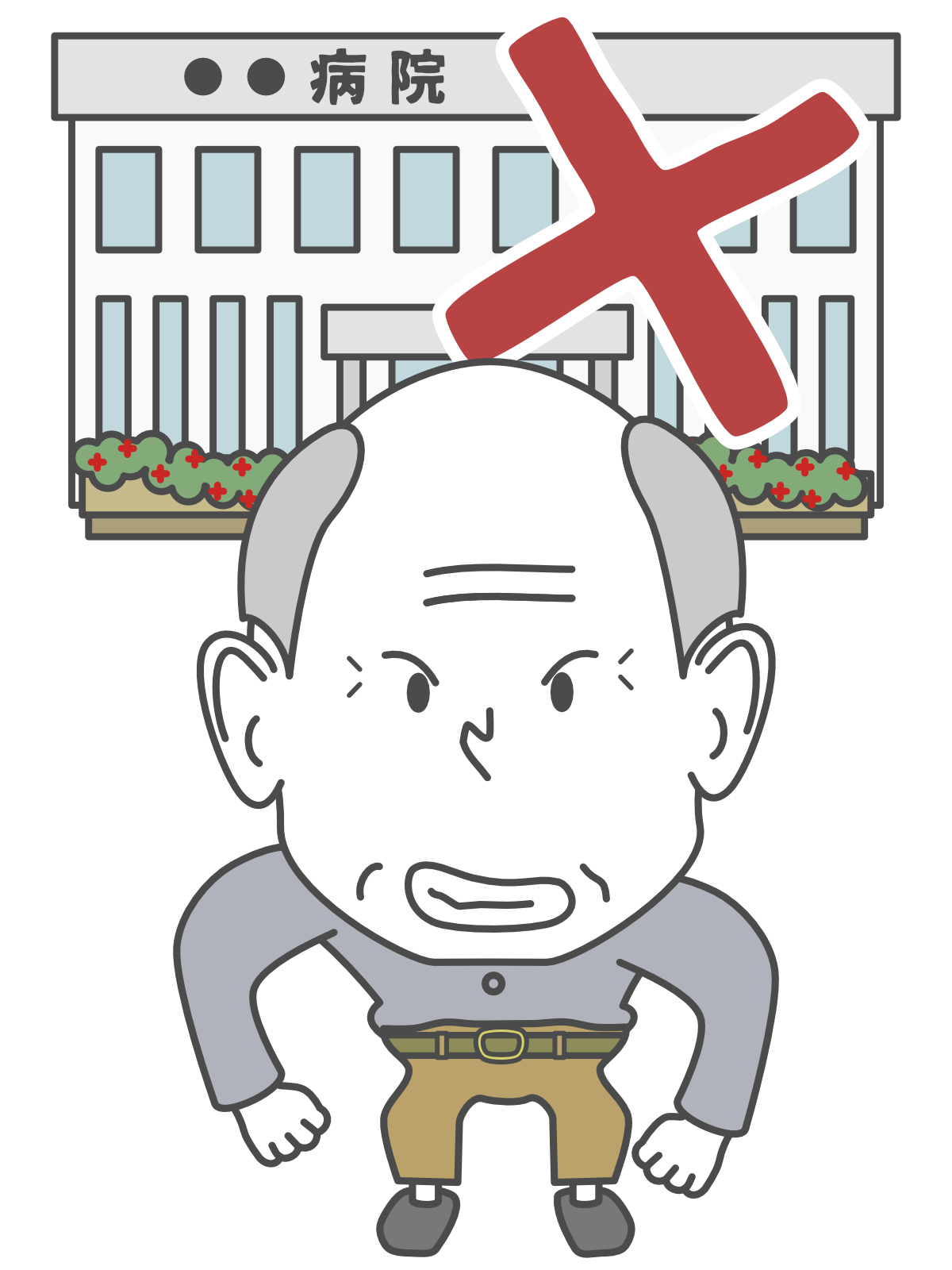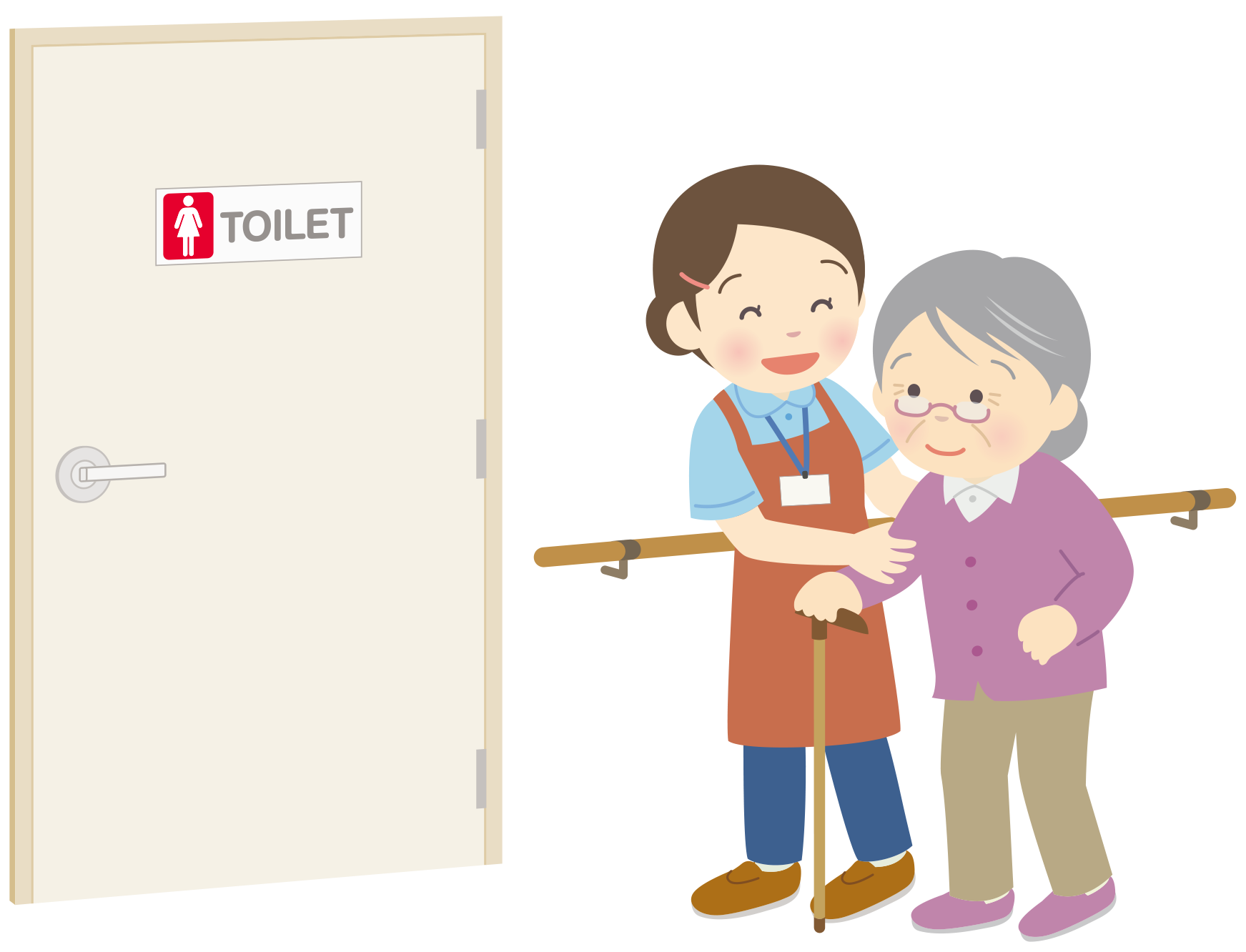物忘れに対する適切な対応とは
2025.08.05

こんにちは。
突然ですが、 「今日は何日?」 「これからどこに行くの?」
認知症のある人からこのような質問を受けたとき、皆さんはどのように対応されていますか?
① 思い出せるまで考えてもらう
② 正解を伝える
③ 確認手段を伝える
「自分で考えた方が脳トレになるのでは?」といった理由で ① を選ばれた方も多いかと思いますが、 認知症ケアでおすすめするのは ②と③ です。
今日は 認知症の症状と脳の仕組み という視点から、その理由をご説明します。
認知症の記憶障害と脳の仕組み
認知症には 「近時記憶の低下(一般的には短期記憶と呼ばれる事が多い)」 という症状があります。 これは 3〜4分前から数日前の比較的近い出来事を思い出しにくくなる というものです。
健常の方であれば、ヒントを与えたり時間をかけたりすれば思い出せることもありますが、 認知症の人の場合、症状が進行するほど、ヒントや時間に関係なく思い出すことが難しくなります。
そのため、上にあげた①は「心当たりのない記憶を無理に作り出す」 作業になってしまうことがあります。
さらに一度誤って作られた記憶は 修正しにくく、同じ誤りを繰り返す という脳の癖があるため、 誤った答えが定着してしまうというデメリットがあります。
認知症の人への適切な対応
② 正解を伝える ③ 確認手段を伝える
この2つの方法の方が、認知症の方にとって より効果的 です。特に MCI(軽度認知障害)~初期の認知症の場合、 ③の確認手段を伝えることで、思い出せなくても、その手段を活用する事を学習し、習慣化できることがあります。
例えば、
・カレンダーや手帳を指さして「今日は病院に行くよ。わからない時はここを見てね。」といった対応です。
また当院でも提供していますが、最近では認知症の人にICTを活用し、定刻にリマインドメッセージをお送りしてそれに基づいて行動して頂くという、忘れやすい事に対してテクノロジーを活用して自立支援を行う方法もあります。介護するご家族の負担感軽減にも繋がりますので、良ければ参考にしてみてください。
■執筆者情報
この記事は、医療法人バディ公式LINE「ケアコミ」の内容を引用しております。

医療法人バディ 認知症部門部長
前田 順子(言語聴覚士・認知症ケア専門士)
2005年から都内の急性期病院に言語聴覚士として勤務。認知症疾患医療センター内での、入院ケア、認知機能検査、認知症カフェの運営等、認知症のある方やご家族のケアに携わった豊富な経験をもつ。
2020年より医療法人バディにて認知症部門立ち上げ。コミュニケーションを主軸とした認知症の非薬物療法に取り組む。ICTを活用した居宅支援「オンライン認知症ケアプラス®」、スターバックスとのコラボによる認知症カフェ「ウェルビーイング☆カフェ鎌倉」等の企画・運営を担当。

医療法人バディ https://buddymedical.jp/
2019年設立。横浜市、鎌倉市に3つの脳外科クリニックと認知症部門を展開。2023年より、居宅介護支援事業、訪問リハビリ。2024年より訪問看護部門を開設。